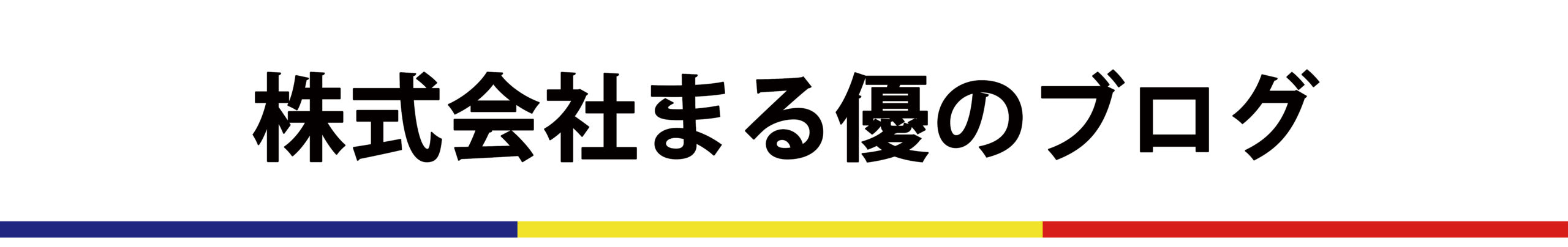アルコールと良い関係を保つ鍵も、腸にある【分子栄養アドバイザーによる大人のイキイキ腸活通信vol2】
皆さん8月は夏らしいことを楽しまれましたか?残暑が続き、風鈴の季節はまだまだ続きそうですね。夏と言えば、毎日のご褒美に、そしてイベントなどで、お酒を飲む機会が多い季節です。でも、お酒ってやっぱり体に悪いのかな、と気にしている方も多いかもしれませんね。
今月は、そんな方に向けて、「腸とアルコール」という切り口で書いていきます。 アルコールの摂取は、腸内細菌バランスを崩壊させ、全身の炎症、肝疾患などの組織損傷に繋がります(Alcohol Res. 2015; 37(2): 223–236.)。
これに関連する報告をいくつかご紹介。
- アルコール中毒者の腸内環境は崩壊している(Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2012 May 1; 302(9): G966–G978.)。
- 合計99名の、アルコール依存症及び肝硬変患者のメタゲノム調査の結果、これらの患者は腸内良性菌が少なかった(Microbiome. 2017 Oct 17;5(1):141.)。
- マウス実験で、慢性的なアルコール摂取が、腸内細菌バランスの悪化や、アルコール性肝疾患の原因になった(PLoS One. 2013;8(1):e53028.)。
このような報告等から、「腸内環境を整えること」は、アルコールが及ぼす腸や肝臓への悪影響の、「予防」になるのではと考えられています。
私たちの腸内に生息する100兆個もの腸内細菌たちは、私たちと同じように、餌を食べて生きています。彼らの餌は、「私たちが食べたもの」。
私たちが食べたものは、胃や小腸が消化吸収し、残りは大腸に運ばれます。この大腸に到達したものを、腸内細菌たちは餌にしているのです。
だから、私たちにとって有益な良性菌(乳酸菌やビフィズス菌)を増やす1つの方法は、良性菌の「餌」を増やすこと。
良性菌の餌になるのは、食物繊維やオリゴ糖など。米や野菜など食事から摂ってもいいですし、サプリメントから摂るのも一つの手段です。(ちなみにお米は、冷やしてから食べるのがお勧め。冷やす過程でレジスタントスターチという食物繊維に似た物質が増えます。)
病気レベルでない人にとって、健康のためにアルコールを泣く泣く止めるというのは現実的ではありません。楽しく美味しいアルコールとうまく付き合うためにお酒を飲むときは、特に腸内環境を意識する。
沢山お酒を飲むなら、いもの食事で足りない分は、サプリで効率的に補っても良いのです。
そして何より大事なのは、普段から、ちょっとやそっとじゃビクともしない腸内環境を作ること。何かを食べる時は、腸内で飼っているペット(良性菌)のことも考えてあげてくださいね。
この記事を書いた人
table project代表 分子栄養アドバイザー
夏木彩早 (公式ラインはこちら>>)
九州大学卒業。臨床分子栄養医学研究会認定指導カウンセラー。長年のニキビや腸過敏で悩み、健康食を研究しまくった末、分子栄養学に出会う。「体調不良に邪魔されず、自分らしく生きる人」を増やすべく、2018年に起業。延べ500名に、科学的な健康食を伝えてきた。現在は、分子栄養学をベースに考案した「個人差食事メソッド」を使い、不調に悩む女性や、専門家向けの講座を運営。天神ホリスティックビューティークリニックでの栄養指導等もおこなっている。